
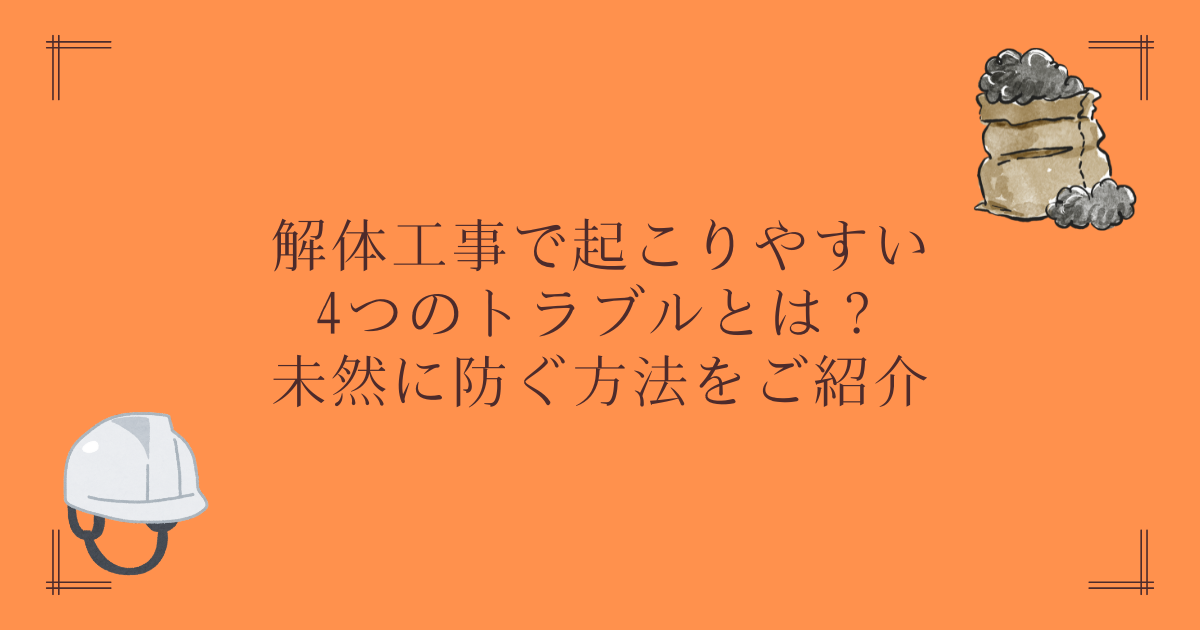
解体工事は、その後の土地活用や売却をスムーズに進めるために必要ですが、
など、予想もできないトラブルが発生する可能性もあります。
しかし、どんなトラブルが起こるのか、どのように対処すればいいのかを知っていれば、過度の心配は必要ありません。
この記事では、実際に起こりやすい解体工事のトラブル事例と、具体的な予防策を解説していきます。

解体工事のトラブルを防ぐには、何がトラブルの原因になるのかを知っておくことが大切です。
ここでは、トラブルの原因と対策を具体的に解説していきます。
解体工事で発生する、騒音・振動・粉塵は、近隣住民にとって大きなストレスとなります。
騒音や粉塵は、感じ方に個人差があるため、数値上の基準だけでなく、ストレスを与えないように配慮することが大切です。
そのためは、工事開始の1週間前までに、業者と連名で挨拶回りを行うのが理想です。
その際、工事期間や作業時間、具体的な対策(防音シート、散水、低騒音重機の使用など)を記した書面を渡します。
特に粉塵対策の散水や養生シートの使用が不十分だと、近隣からの苦情に直結するため、これらを徹底する業者を選ぶことは重要です。
また、重機搬入日は特に騒音が大きくなるため、事前に『◯日は振動が強く出る見込みです』と伝えるだけでも効果があります。
解体工事を請け負う業者は、法律に基づいて適切な許可や登録を受ける必要があります。
請負金額が500万円以上の場合は建設業許可、500万円未満の場合は解体工事業登録といった具合です。
また解体で発生した産業廃棄物を処理する際にも、廃棄物が適切に処理されたことを証明するマニフェストの交付と、最終処分までを記録する義務もあります。
もしマニフェストの提出を怠ったり、不法投棄を行ったりした場合、施主にも責任が及ぶ可能性があります。
そうならないように、契約前に許可・登録の有無と、マニフェストを適正に運用しているかを必ず確認してください。
解体工事で起こる最後のトラブルは、アスベストと産業廃棄物の不適正処理です。
古い建物には、発がん性のあるアスベスト含有建材が使われている可能性が高く、2022年4月からは、解体前に専門家による事前調査を行い、その結果を自治体に報告することが義務付けられています。
そのため優良な業者は、アスベスト調査費用を明確に見積もりに含めてくれるほか、含有が確認された時は、法令を遵守した除去計画を提案してくれるでしょう。
また産業廃棄物が出たときの処分方法や費用などの情報も、事前に知っておくと安心できます。
アスベストの詳しい情報については「解体工事とアスベストの関係は?知立市での注意点や対処法を解説」をご覧ください。
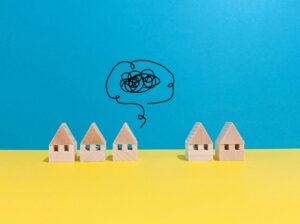
ここでは、現場で発生しやすい具体的なトラブル事例と原因について解説します。これらの事例を知っておくことで、事前に具体的な対策を業者に求めることができるでしょう。
解体工事で最も件数が多い苦情は、騒音と振動に関するものです。
特に、重機が頻繁に出入りしたり、重機による建物の破砕作業や資材の積み込み作業で発生する衝撃音は隣家に伝わりやすく、家が揺れていると感じさせてしまうことがあります。
主な苦情の内容としては「乳幼児が昼寝できない」「夜勤明けなのに眠れない」「リモートワークに支障が出る」「棚のものが落ちた」などです。
これを防ぐには、業者が低騒音型の重機を所有しているか、作業時間の厳守を徹底しているか、などを確認することが大切です。
解体する建物に使用されていたコンクリート・木材・土に含まれる微細な粒子が風に乗って、近隣の洗濯物や車、庭に入り込むと苦情に発展することがあります。
一例として、「窓を開けられない」「車が汚れた」「アレルギーが悪化した」などです。
中には、建物の隙間に潜んでいたゴキブリやネズミなどの害虫が解体によって逃げ出し、隣家に侵入したという苦情もあります。
対策としては、高圧散水を徹底して行うことや、建物を養生シートで隙間なく覆うなどがあります。
このような作業を業者が徹底してやってくれるかを見届けることも、苦情に対応する方法の一つです。
狭い生活道路で工事を行う際、業者が資材を道路上に置いたり、車両を路上駐車して、近隣の家の前を一時的に占有することで、通行の妨げとなりトラブルに発展することがあります。
通学路の安全が脅かされたとして警察に通報されることや、誘導員を配置していないために接触したというトラブルも起こっています。
対処法としては、業者の現場管理体制を確認したり、契約時に路上駐車は厳禁であることや誘導員の配置について明記してもらうなどがあります。
解体業者の中には、処理費用を削減するために、解体で出た木材やコンクリートガラなどの産業廃棄物を不法に投棄したり、解体現場の地中に埋めたりする悪質な業者が存在します。
不法投棄は、施主も法的な責任を問われる可能性があり、後日発見された際に撤去費用を請求されることもあります。
これを防ぐためには、マニフェストの確実な交付と、最終処分場を記載した書類を業者から受け取ることを契約書に明記することが大切です。
まずは、業者からの挨拶や説明があったかどうかを確認してください。
挨拶がなく、不安を感じる場合は、工事業者の看板に記載されている連絡先に問い合わせ、工事期間や騒音・粉塵対策について説明を求めることができます。
また、工事によるヒビや破損が生じていないかを確認するために、事前に写真や動画で記録しておくと安心感があります。
万が一、被害が発生した場合は、工事業者へクレームを入れ、対応が不十分であれば、役所の環境課や、国民生活センターに相談することも検討できるでしょう。

解体作業中に隣家の壁にヒビが入ったり、窓ガラスが破損する物損事故が発生する可能性はゼロではありません。
このような事態に備え、業者が保険に加入しているか、そして万が一の時にその保険が適用されるかを確認してください。
例えば、建設工事保険、請負業者賠償責任保険、施設所有管理者賠償責任保険、第三者賠償責任保険などがあります。
また工事前には、隣家の外壁などの現状写真を撮影し、記録に残すこともできます。
万が一の損害が発生した際に、破損が解体工事によって生じたものかを客観的に判断する大きな材料になるからです。
見積もり書は、不当な追加費用トラブルを防ぐための最重要書類です。
以下の項目が「一式」ではなく、具体的な単価や数量で明記されているかを確認してください。
地中埋設物については「発見された場合は、別途協議のうえ費用を決定する」といった明確な取り決めを事前に交わしておくことで、高額な追加請求を回避できます。
また、1社のみに見積もりを依頼するのでなく、できれば3社以上から取り、単価差が大きい項目を質問すると業者の説明力と透明性を判断できます。
工期が延びることは、近隣住民のストレスを増大させるため、契約前に天候不順や地中埋設物が発見された時に、工期を延長するかどうかの基準を明確にし、余裕を持った工期を設定してもらいましょう。
また、足場の設置範囲についても、隣家との境界線近くに設置する場合や、一部の敷地を一時的に借りる必要がある場合は、業者から近隣へ細かく説明してもらう必要があります。
こういった細かな情報や作業範囲を事前に共有することで、工事中の認識のズレを防ぎ、トラブルが起きる可能性を下げます。

どれだけ入念に準備をしても、人の感じ方や予期せぬ事故で苦情をゼロにするのは困難です。
そこで重要になってくるのは、苦情が来た時の初動対応です。
迅速かつ誠実に対応することで、トラブルの深刻化を防ぐことができます。
苦情が来た場合の窓口は、原則として解体業者が担います。施主が直接対応すると感情的な対立に発展しやすいため、業者に一任するのが得策でしょう。
業者は、苦情を受けたら以下のようなフローで対応するのが一般的です。
解体工事が原因で隣家に物理的な損害が発生し、損害賠償請求が視野に入った場合、まず必要となるのが、損害が解体工事に起因することを証明する書類です。
損害の状況を写真で記録した後、建築士事務所などの第三者機関に依頼して、損傷が工事によるものかを判断する、家屋調査報告書を作成してもらいます。
その際、業者が加入している第三者賠償責任保険などを利用し、保険会社を通じて賠償額の交渉を行います。
苦情が損害賠償や裁判に発展し、当事者同士での解決が困難になった場合は、弁護士に相談してください。
費用の問題で弁護士への相談をためらう場合は、国が設立した法テラス(日本司法支援センター)を利用することで、無料の法律相談や弁護士費用の立替制度を利用できます。

施工実績の確認は、自分が住んでいるエリアでの実績があるか、木造・鉄骨・RC造など、様々な構造の解体実績があるかに注目できます。
また、写真だけを掲載しているのではなく、アスベスト対策・近隣対策・産業廃棄物処理など、トラブル回避に関する具体的な取り組みや考え方が明記されているかどうかもチェックできます。
見積もりを比較する際は、最終的な総額だけを見るのではなく、以下の3点を重点的に比較してください。
最終的な契約書には、以下の項目を盛り込むようにし、施主と業者の責任範囲を明確にしましょう。
この記事では、解体工事で起こりやすい4つのトラブルを未然に防ぐ方法をご紹介しました。
まとめると
この、4つとなります。
私たち藤原建設は、単に建物を壊すだけでなく、地域社会の調和を重視し、トラブル発生率ゼロを目指した丁寧な現場管理を徹底しています。
工事前の近隣への挨拶回りから、騒音・粉塵を最小限に抑える対策まで、細部にわたり徹底的な配慮を行います。
地元での信頼を重視する藤原建設が、近隣との関係を大切にした円滑な工事を実現いたします。
解体工事に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。